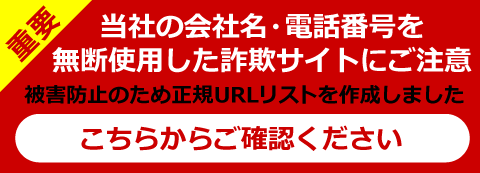お墓の引越しやご遺骨の移動に必要な「改葬許可申請」について手続きの流れなど詳しく解説!

お墓を建てる機会は人生にそう何度もある事ではありません。お墓を建てる手順が分からない、誰かに相談する前に自分で調べておきたいという方もいらっしゃるかと思います。
そんな方々のために今回は「建墓」について詳しく解説いたします。
建墓(お墓建立)とは
お墓を建てることを建墓(お墓建立)といいます。
建墓後「開眼供養」というお墓に魂を入れる儀式を行うことで、お墓として完成します。
開眼供養は魂入れ、入魂式とも呼ばれ、お墓であると定めるもの、またはお墓の引越しの際に移されるご遺骨に、新しいお墓であることを示す意味合いがあります。
お墓を建てるタイミング
一般的には、四十九日や一周忌を迎えるまでに建墓します。
多くの場合、お墓が出来上がるのに1~3か月かかると言われています。これはあくまで建墓の工事期間であり、墓地選びやお墓のイメージ・デザインに関する打ち合わせなどが済んでいない場合、さらに時間がかかります。
四十九日や一周忌に間に合わせるよう、急いで建墓する方もいらっしゃいますが、その時期までに絶対建てなければいけないということはありません。
急ぐあまり費用が膨れ上がったり、工事が不十分だったりと失敗してしまう恐れもあります。お墓選び・建墓は余裕をもって行うことが大切です。
お墓を建てるときの流れ
- 01墓地の確保
-

墓地には大きく分けて「お寺が運営する墓地」と「公営・民営の墓地」の2つがあります。
お寺が運営している墓地は檀家になる必要があるため、今後、檀家として寄付などを求められることもあるかもしれません。お寺が運営する墓地はご自身の宗派からお寺を探すことになります。
公営墓地は、自治体が管理しており檀家になるよりも安い費用で使用できますが、競争率が高く抽選に当たらないと利用できません。
民営墓地は、施設が充実している等のメリットもありますが、公営よりは費用が高い事、いざお墓じまいをとなった時に、指定石材店制度により費用が抑えられないというデメリットもあります。
- 02石材店さんとの打ち合わせ
-

墓地が決まったら、石材店にお墓を建てる相談をします。石材店さんは葬儀を行った葬儀社に相談すると紹介してもらえるケースもあります。民間墓地の場合は石材店が指定されているケースもあるので、確認が必要です。
墓石の材質、形や付属品、墓石に刻む文字など希望することを伝え、詳細を詰めていきます。
墓石の形も、最近では昔ながらの縦型だけでなく、洋風のお墓を建てる人も増えています。ただし、洋風のお墓は墓地によって制限がある場合もあるので、注意が必要です。
- 03工事
-

打ち合わせがまとまったら実際に工事を進めます。よくある縦型のお墓の場合、初めに地盤を固めて外柵を設置し、延べ石を構え、石碑を立てたら工事完了です。
工事は基本的に立ち合いの必要はありません。どうしても気になる場合や工事を見届けたい場合は現地まで行き、立ち会うことも可能です。
- 04引き渡し
-

工事が完了したら契約内容の通りに工事が完了しているかどうか確認をし、問題が無ければ引き渡しとなります。引き渡しまでは、石材店での契約から墓地の据え付けのみであれば一か月、デザインから依頼した場合は2~3か月ほどかかります。
- 05納骨・魂入れ供養
-

仏式の場合、完成したお墓で「開眼供養」という儀式を行います。
開眼供養とは、新しいお墓に故人の魂を宿す儀式で、何もない状態から命あるお墓に変えるものです。「魂入れ」や「御魂入れ」などとも呼ばれています。
開眼供養では、お坊さんに読経をお務めいただき、納骨と並行して行われることが一般的です。
お墓建立の費用相場
お墓を建てる際の全体的な費用相場は約100万円~150万円ほどと言われています。
一昔前は上記の3~4倍の費用がかかるともいわれていましたが、現代ではお墓のコンパクト化などにより、費用も抑えられるようになりました。
お墓を建てるためにかかる費用は、大きく分けて次の3つです。
墓石・工事代
- 相場
- 60~200万円
シンボルとなる墓石のほか、外柵やカロートなどの石材費・加工費・彫刻費・設置工事費用になります。墓石の種類やデザイン、墓地の立地によって金額は大きく異なります。
永代使用料
- 相場
- 30~100万円
墓所を使用する権利に対する費用の事です。墓地のある地域や広さ、環境などで相場が変動します。
管理費
- 相場
- 5千~1.5万円
墓地のトイレ、水汲み場、通路、緑地などの共用スペースの維持・管理に使用されるもので、年額で設定されているケースが多いです。
お墓を建てる費用を抑えるポイント
お墓を建てるのは、多大な費用がかかるため「金銭的に厳しい」と感じる方もいるでしょう。
そこで、お墓の費用を抑えるポイントをご紹介します。
都心部を避ける
都内や駅から近いなど好条件の墓地はそれだけ費用も上昇します。都心部を避けることで費用を安く抑えることができます。
お墓の区画を狭くする
お墓の区画の広さを狭くすることで費用を抑えることができます。全体的な予算を見て、一部抑えたい場合は区画の広さを検討することで費用の調整が可能です。
墓石をシンプルにする
墓石のデザインを凝ったものにしたり、彫刻をオーダーメイドした場合、その分彫刻費や作業費が高くなります。
なるべくシンプルなデザインにして石材を少なくすることで、費用を抑えて建てることができます。
希望に合った墓地の運営団体を選ぶ
墓地の運営団体は主に「お寺」「民間の霊園」「公営の霊園」の3つです。
費用面で見ると公営霊園が安い傾向にありますが、それぞれメリット・デメリットが存在するので、希望に沿った墓地の運営団体を見極めることが大切です。
お墓を建てる以外の供養方法
最近では墓守の問題やライフスタイルの変化により、お墓を建てない選択を選ぶ方も多くなっています。
そこで、墓石を立てる以外の供養方法についてご紹介します。
永代供養墓

永代供養墓とは、墓地・霊園やお寺さんに供養・管理をお任せするお墓です。
お墓の跡継ぎがいない方や、負担を残したくない方に選ばれることが多いです。墓石を必要とせず、土地スペースの準備もないため、お墓を建てるより費用を抑えることができます。
樹木葬

樹木葬とは、墓石を使わずシンボルツリーを植えてその下に納骨するスタイルのお墓です。
永代供養してくれる樹木葬も多く、庭園スタイルや和風スタイルのものなど、自分好みのものを選べることから近年人気となっています。
納骨堂

納骨堂とは、建物内のスペースの中から1つ借りてお骨を収蔵する方法の事です。
ロッカーや棚に納めるものから、個別の部屋で遺骨を安置できるものなど様々な納骨堂があります。
市街地などにあることが多いため交通の便が良いことが多く、天候に左右されないためお墓参りがしやすいといった特徴があります。
散骨

散骨とは、遺骨をパウダー状にして海や山に撒いて供養する方法です。
散骨は多くの場合、散骨を行う業者に依頼することが一般的です。お墓を建てる費用のおよそ10分の1程度で済む可能性もあり、経済的な供養方法になります。
手元供養

手元供養とは、自宅など手元に置いて供養する方法です。
全骨と分骨の方法がありますが、分骨の場合に手元供養を選ぶ人も増えており、最近ではペンダントやブレスレットなどにして身に着けるケースもあります。
墓石や墓地の費用が掛からないため費用を抑えることができます。
まとめ
今回は、お墓を建てるのに必要な費用や手順などについて解説しました。
お墓を建てるには、きちんとした手順を踏んで手続きや費用の支払いなどを経るのが一般的です。
また、お墓を建てる以外の供養方法もあり、費用を抑えたい方や跡継ぎ問題を解消したい方は建墓以外の方法を検討するのも一つの手です。
終楽市では、お墓の建立・建墓に関するご相談を全国で受け付けております。260社以上の石材店さんと提携しており、ご依頼があったエリアに対応できる業者さんをご紹介いたします。
弊社が窓口となり、安心・安全なお墓の建立をお手伝いいたします。