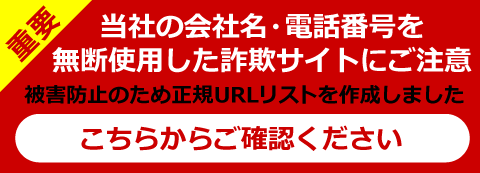お墓の土地、所有権は誰のもの?相続方法や継承について詳しく解説!

実家のお墓を引き継ぐ予定だけどどういった手続きが必要なのかわからない、お墓の土地って売却できるの?といった疑問を抱く方も多いかと思います。
この記事ではお墓の所有権や相続について解説します。
お墓の相続者(継承者)の決め方
日本では昔から「お墓を管理する人が亡くなると、嫁や子供など身内がお墓を相続する」というのが一般的でした。しかし、時代が変わり「相続する子供がいない」「お墓が遠方にある」といった理由で相続人が決まらないことも増えてきました。
ここでは、お墓の相続人について解説します。
お墓の相続人に法律上の決まりはない
お墓を相続する人について法律上の決まりはありません。そのため、一般的には一家の長男・長女がお墓を相続するというのが慣習になっています。
ただし、「祭祀財産」を相続するのは一人と決まっています。祭祀財産とは民法によって定められている「系譜」「祭具」「墳墓」の3つです。そのため、「お墓は長男、仏壇は長女が引き継ぐ」といった分割の相続はできません。
遺言や慣習で決まることが一般的
お墓の相続人は個人の遺言や一家の慣習で決まるのが一般的です。ただし、相続人がなかなか決まらないといった場合は家庭裁判所の調停、審判で決めることになるでしょう。
相続人は、結婚して家を出た子供や血のつながりが無い姻族、故人の親族も対象です。
霊園の使用規則に条件がある場合も
中にはお墓の相続人の条件を定めている墓地や霊園もあります。例えば「今までの墓地使用者の3親等以内の親族である」などです。遠い親戚や内縁の妻・夫が相続したい場合は注意が必要です。
相続人を決める前に一度墓地や管理者へ問い合わせておくことが大切です。
祭祀継承者の役割
「祭祀継承者」とは、お墓を相続する人の名称です。祭祀継承者は、お墓に関する様々な事を管理する必要があります。
ここでは祭祀継承者の役割について説明します。
お墓の維持や管理
故人を偲ぶ命日、彼岸、お盆に供えてお墓の手入れをするなど、お墓の維持・管理をします。
お墓がある場所によって、維持管理費が必要になります。祭祀継承者はお墓を維持するのに必要な費用を支払う役割もあります。
お墓・遺骨の所有権を持つ
お墓そのものやご遺骨に対して所有権を持ちます。お墓やご遺骨の管理方法を変更したい場合、祭祀継承者の同意を得る必要があります。
同意なく墓地や遺骨を移動するとトラブルの元となります。
法要の主宰
一周忌や三回忌をはじめ、定期的に行う法要の主宰も務めます。祭祀継承者には、親族や寺院への連絡や手配などの法要を取りまとめる役割もあります。
お墓の土地の所有権と使用権の違い
お墓を建てている土地は一般的に購入する物ではなく、墓地の使用権を購入もしくは継承されているケースが大半です。
ここではお墓の墓地の所有権と使用権の違いについて解説します。
墓地の使用権のみ取得している場合
一般的にお墓を建てる場合は、土地を購入するのではなく、墓地の使用権を購入することを意味します。使用権を付与する墓地や霊園は、以下のものが挙げられます。
- 公営墓地(市町村が運営)
- 共同墓地(集落単位で運営)
- 民営墓地(公益法人等が運営)
- 寺院墓地(お寺が運営)
墓地や霊園を運営している所から購入した使用権を「永代使用権」といい、このお権利があれば墓地の一区画を永久に使用できます。
お墓じまいなどでお墓を畳む場合、永代使用権は墓地・霊園へ返還しますが、基本的には永代使用権を返還してもお金は戻ってきません。
墓地の所有権を取得しているケース
所有する土地の敷地内にお墓を立てた場合は、墓地の所有権を取得しているといえます。
土地の所有者が亡くなり相続が発生すると、墓地は祭祀を営むために必要な「祭祀財産」とされ、相続財産と分離されます。継承した人は、登記申請をして名義変更をします。
永代使用権・永代使用料・永代供養の違い
永代供養・永代使用権・永代使用料とどれも「永代」とつきますが、3つの用語の意味はそれぞれ異なります。
永代使用権
お墓を建てるための土地を使用する権利を「永代使用権」といいます。土地を購入するのではなく、永代に渡り使用する権利で、所有権ではありません。譲渡や売買はできませんが、祭祀財産として承継可能です。
永代使用料
お墓を建てる寺院や霊園に支払うのが永代使用料です。
一般的に契約時に一括で支払いますが、永代使用料とは別に年間管理料を毎年支払う場合が多いです。年間管理料の支払いが滞ると使用権を失う場合があります。
永代使用権を得たら、使用権を承継できますが、お墓を継ぐ者がいなくなった場合、その権利は失効し返還されます。
永代供養
永代供養とは、ご遺骨の供養・管理を永代に渡り寺院や霊園に委託する方法のことです。
身寄りのない方やお墓じまいをした方などが利用されることが多いです。
お墓の相続方法・手続きの流れ
お墓の相続手続きは公営・民営墓地、個人墓地などによって手続きが異なります。
それぞれの相続手続きの流れについて解説します。
個人墓地の場合
所有する土地の敷地内にある墓地を個人墓地といい、土地の所有権を祭祀承継者に移転させる必要があります。土地の所有権を移すには、以下の書類を法務局に提出します。
また、個人墓地のお墓を相続する場合、登録免許税はかかりません。
- 登記申請書
- 登記識別情報
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本
- 相続人の現在戸籍と住民票
- 遺言書または遺産分割協議書
公営・民営・寺院墓地の場合
個人墓地と違い、法務局の登記は不要ですが、永代使用権の名義変更が必要になるので、以下の書類を墓地・霊園などに提出します。
- 名義変更申請書(墓地や霊園の指定様式)
- 墓地使用許可証又は永代使用承諾証(被相続人が取得したもの)
- 現在の墓地使用者の死亡が確認できる戸籍・除籍謄本
- 祭祀承継者の現在戸籍と住民票
- 祭祀承継者の実印と印鑑証明書
- 祭祀継承者であることを証明する書類
祭祀継承者であることを証明する書類は、墓地使用者との関係がわかる戸籍謄本や葬儀費用の領収書、遺言書や親族の同意書などがあります。
また、名義変更の手続きの際、必要書類と一緒に手数料も支払います。手数料の金額は霊園によって異なりますが、おおむね1,000~5,000円程度となっています。
- 公営墓地
- 公営墓地の場合、数百円~数千円程度の所が多いです。
- 民営墓地
- 民営墓地の場合、霊園によって大きく異なります。数千円程度のところから1万円以上するところもあります。
- 寺院墓地
- 寺院墓地の場合、檀家としての立場もお墓と共に引き継ぐことになるので、手数料に添えて御布施を包むことがあります。お布施はそれまでの寺院との付き合い方によっても変わってくるので、直接お寺に相談すると良いでしょう。
お墓を相続する人がいない・管理ができない場合
お墓を相続する人がいない、誰も祭祀継承者になりたがらない、お墓が遠方にあって管理できないなど、お墓を維持することが難しい場合は以下の方法を検討することをおすすめします。
お墓は相続財産でないため、相続放棄の対象外になります。お墓の管理や祭祀については、必ず誰かが引き継がなくてはなりません。
お墓を改葬する
お墓が遠方にあり維持・管理が難しい場合は改葬を検討してみましょう。
改葬とは、現在のお墓から別のお墓に遺骨を移して埋葬する方法の事です。お墓の改葬には様々なパターンがあり、費用もそれぞれ異なります。
お墓じまいをする
祭祀継承者となる人がおらず、お墓の維持や管理ができない場合、お墓じまいも選択肢になるでしょう。お墓じまいは墓石を撤去し、墓地を返還、ご遺骨を別のお墓や永代供養墓へ改葬するケースが一般的です。
ただし、お墓じまいにはお墓の撤去費用だけでなく、離檀料やお布施、改葬先の納骨費用、必要書類の取得費など様々な費用がかかります。
家庭裁判所にて調停・審判を申し立てる
お墓の相続や祭祀継承者を決めるのに相続人同士がもめてしまった場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立ててみましょう。調停の場合、話し合いによって解決を目指しますが、調停委員を交えるため調停開始・終了時でしか当事者同士が顔を合わせることはありません。
調停が不成立になった場合、審判へ移行し、裁判官が祭祀継承者を指定します。
調停や審判は提出書類が多く、自分の主張を裏付ける証拠なども必要になるので、必要に応じて弁護士に相談すると良いでしょう。
まとめ
今回はお墓の相続・継承について詳しく解説しました。
お墓は祭祀財産となるため、相続放棄をしてもお墓は承継しなければなりません。
祭祀継承者を決めるのにもめてしまった場合は家庭裁判所へ調停・審判の申し立てを行い、必ず祭祀継承者を決めましょう。
また、祭祀継承者となる人がおらず、自分が最後の祭祀継承者となってしまった場合は、お墓じまいをしなければいけません。お墓の相続・承継で問題や分からないことがあれば弁護士に相談するのが良いでしょう。